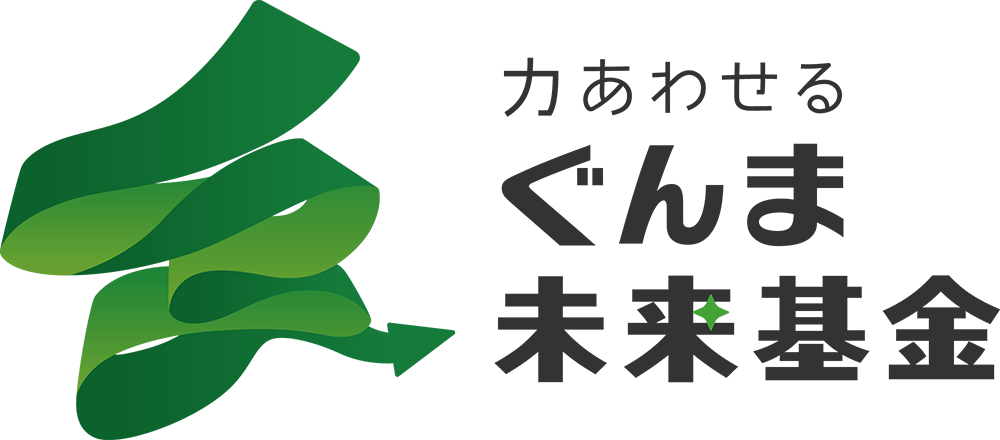地域別支援助成2025 採択7団体紹介


1.東毛地域 わがままパークプロジェクト
事業名 「子どもたち主体」の私設公園づくりで、芽ぶく自治
“公園(パーク)づくり”から、まちの自治をリノベーションする:大間々六人衆や三方良しの会など、江戸時代に町の礎を築いたことに始まり、現代の情報発信を地域住民自身が行う自治の土壌のある群馬県みどり市大間々町。次代の自治の形として、遊休不動産をリノベーションで公園(パーク)とするハード面の整備と、まちの人同士で、これからのまちを考え・人同士のつながりを育んでいくソフト面の仕組みをつくる。「あったらいいな」を専門家の知識と技術を掛け合わせ具現化、まちの人がまちに関わる機会を生み出す。
2025 年 4 月から月 1 回、全 5 回(+自由参加のスペシャル企画1回)のプログラムで、みどり市の小学3〜6年生10名を対象とした施設公園づくりのワークショップを武蔵野大学建築デザイン学科「OTA LAB」の学生 9 名+講師 1 名と連携して実施。ワークショップ自体は既に始動しているが、本助成では 8/1(金)- 8/3(日) ワークショップ大間々祇園祭での「おひろめ会」をメインとして申請を行う。
多くの人が集まる大間々祇園祭を絶好のPRの場として活用し、子どもたちが主体となって設計を行なった「わがままパーク」の遊具や空間の模型を展示したり、ワークショップ時の様子を展示しながら、来場者に子ども達自らが説明を行うポスターセッション形式でのお披露目会を実施する。
本事業を通じて子ども達がゼロから建築学生たちと築き上げてきた有休不動産の未来図を来場者へ直接伝え、意見交換を行う過程を通じて「自分たちの住むまちを、自分たちの手で豊かにすることの大切さ」を学ぶきっかけとしてもらい、家族・学校以外の多世代との関わりによって第三のコミュニティ形成の一助とする。
2.中毛地域 社会福祉法人 上毛愛隣社
母子生活支援施設 のぞみの家
事業名 のぞみの家 母子旅行
のぞみの家に入所している母子は、事情があって父親や家族と一緒に生活をすることが出来ない母子です。母が抱えている課題は多岐にわたります。特に子育てに悩みや不安を抱えている母が多いです。同様に、ほとんどのこどもたちが被虐待児で母との愛着関係は希薄です。親に大切にされた経験に乏しく、たくさんの問題を抱えています。親子関係はもちろんのこと、地域からも孤立していた世帯です。
母がこどもをディズニーランドに連れていくなどは期待できず、「施設が企画をしなければこどもたちは一生行くことが出来ない」と言っても過言ではありません。本助成を活用し、母子旅行でディズニーランドへ行くことで、より良い親子関係の構築につながるのではないかと考えます。楽しい思い出は、幸せな気持ちにさせてくれます。今後の母子支援に有効に作用することが期待されます。
3.中毛地域 子育てネットワークゆるいく
事業名 赤ちゃんから学ぶいのちの授業
子育てネットワークゆるいくは、「みんなの笑顔がいちばん!」をスローガンに掲げ、「人と人とのつながり・いのちのつながり」を実感できる社会の実現を目指しています。現在、核家族化や少子化、地域との関わりの希薄化、情報過多な育児環境といった背景から、子育て中の親が孤立しやすい状況が広がっています。こうした中で、地域全体で子育てを支える仕組みづくりが必要とされています。
私たちのビジョンは、すべての人が尊重され、支え合える地域社会を築くことです。ゴールは、子育てを通じて人と人が深くつながり、自己肯定感をもって生きられる人を増やすことにあります。そのために、親子が愛着の絆を育める場の提供や、地域とのつながりを促す子育て支援活動を行っています。子どもたちのいのちを尊重し、親と子が共に生きる喜びや希望を感じられる場づくりを通して、群馬に暮らすすべての人が笑顔で子育てできる社会を目指します。
前橋市近郊の中学校の授業時間に「赤ちゃんから学ぶいのちの授業」を提供。
1, 授業内容
①妊婦体験 ②赤ちゃんふれあい体験 ③いのちの話
2, 実施対象中学校
実施校:前橋市近郊の中学校 10 校にて実施。実施校は公募。
3, 赤ちゃんゲスト
対象:事業実施日の年齢が 0 歳の赤ちゃんと、その親
4, 実施主体
子育てネットワークゆるいくスタッフ(計 26 人)のうち、8~12 人で運営
4.北毛地域 特定非営利活動法人ミニヨン・スター
事業名 ファミリーホーム〜障害者も高齢者も共に働き、暮らせる場所づくり〜を目指して
第一弾:新しい働くとコミュニティを創出するプロジェクト
第二子に障害の疑いがあり、知り、学ぶことを始めた。その後、平成 11 年に群馬大学が開催していた「療育(りょういく)」イベントに参加したことがきっかけで、同じ想いを持つご家族と出会う。そして、平成 15 年に五つの家族が集まり、障害児の親の会として任意団体を設立した。障害があってもたくさんの経験や体験をさせたい、障害があっても住み慣れた地域でずっと暮らしたい、そんな想いを持った仲間と活動を始めました。日々の取り組みをする中で余暇支援活動に対する新たな壁を乗り越えるべく、平成 20 年に NPO 法人化をし移動支援事業を開始した。障害を持つ本人やご家族はみんな様々な問題を抱えて、個々に頑張っているが限界がある。でも仲間がいれば助け合って、一緒にいろいろなところへ出かけ、様々なチャレンジもできる、何よりも孤独を感じることがなくなる、何でも話せる場所として団体を運営している。
私たちは共に働き、共に暮らすことを目指すコミュニティづくりの活動を始める。第一段階として先進事例を学ぶ講演会を企画し、地域社会内での認知向上と人財の育成を推進していきます。
*ステップ1*
現在障害者の雇用を行っている事業者を講師に招き講演会を実施する。
1. 基調講演 講師:惣万佳代子さん(仮) (NPO法人このゆびとまれ 代表理事)
2. パネルディスカッション 登壇:惣万佳代子さん(講師)・行政関係・労働関係・進行:小林喜美栄
3.参加者交流会
*ステップ2*
障害者の職業体験を実施する。
1. 小売業 対象:障害者区分1~6まで
2. 農業 対象:障害者区分1~5まで
上記のステップ1と2を通じて関係者の交流を促進し、コミュニティづくりを進めていく。
5.北毛地域 特定非営利活動法人のびるっこ
事業名 Digital かかあ天下プロジェクト
渋川市を拠点に、子育てや介護などライフイベントで社会とのつながりが希薄になってしまっている女性を主な対象とし、デジタルスキルの習得により、時間や場所に縛られない柔軟な働き方を実現することを目指すものです。
群馬県が昨年度実施した「IT 人材育成×女性就労支援MAITSURU プロジェクト」にてキャリアスタート講座の講師を務めた専門家を招き、デジタルスキル習得を目的としたオンライン講座 3 回・対面講座 1 回のハイブリッド型講座を実施します。主な対象は、子育て中や復職を目指す女性、また新たな働き方を模索している女性たちです。北毛地域では、県主催のセミナーや都市部の支援サービスにアクセスしにくく、行政による公助が届きにくい側面があります。そこで、地域の女性たちが互いに学び合い支え合う“共助”の仕組みとして、本講座を位置付けます。各講座のテーマは、事前アンケートによって受講希望者の関心やニーズを把握したうえで、講師と相談して決定します。在宅ワークの始め方、IT ツールの基礎、個人事業主としての第一歩など、具体的かつ実践的なテーマを設定予定です。
オンライン講座は Zoom を活用し、定員 50 名とします。デジタルスキルの基本的な使い方から働き方の選択肢まで、初心者でも理解しやすい構成とします。対面講座は定員 30 名に加え、移動が難しい方向けに同時 Zoom 配信(定員 30 名程度)も実施し、育児や介護などを抱える方の参加のハードルを下げます。
講師は、2024 年度 MAITSURU プロジェクトの事業運営責任者であり現在はフリーランスとして活躍する渡辺 由美子氏、「働くことに夢中になれる環境づくり」を掲げる株式会社ワカルクの代表取締役 CEO 石川沙絵子氏に依頼をしています。学びの場に加え、参加者同士が交流し、悩みや知恵を共有できる場づくりも行います。
本講座を通じて、地域の女性たちが新しい働き方や社会との関わり方を見つけ、自立とつながりを育む第一歩となることを目指します。
6.西毛地域 特定非営利活動法人つながるん場
事業名 出張がんサロン
私たちの活動は、がん患者が安心して集い、体験を分かち合える居場所を提供するものです。同じ経験を持つ仲間だからこそ共感し合える場が、新たな一歩を踏み出すきっかけになります。また、地域住民との交流を通じて、がんに対する正しい知識が浸透することで、予防できるがんがあること、がん検診による早期発見の重要性などを自分事として捉えてもらえます。
1 がん患者の悩みや困りごとを丁寧に傾聴し、安心して話せる場を提供します。患者が自身の経験や思いを語ることで、抱える問題や感情に気づき、それに向き合うきっかけを得ることができます。また、同じ立場の人同士が支え合うことで孤立感の軽減や心理的安定を促進し、前向きな行動変容を支援します。
2 がん患者がサロン等の交流の場に参加し、同じ境遇の人の話を聞いたり、自らの体験を語ることにより、一人ではないと実感し、病気への向き合い方や心の持ち方に変化が生まれます。共感と対話によって、希望や安心感が得られ、治療への意欲や生活の質(QOL)の向上につながると考えています。
3 変化の測定には、以下のような客観的・主観的な指標を用います。
・がんサロンへの参加人数やリピート率の推移(客観的指標)
・参加者へのアンケートを通じた心理的変化(不安の軽減、前向きな気持ちの有無など)の定点調査
・支援者による活動記録の分析を通じた行動変化の把握
これらを定期的に記録・分析することで、活動による変化を可視化し、今後の活動の改善にも役立てます。
7.西毛地域 一般社団法人 ぐんまオペラバレエ振興会
事業名 高崎オペラシアター 地産地消オペラ「椿姫」
私共は「地産地消オペラ」という名の下で活動しております。こちらには地元の方々に活躍して頂き、地元の方々にオペラの魅力を楽しんでいただきたいという思いが込められています。オーケストラ、オペラ歌唱、合唱、バレエ。県内ではそれぞれの分野では各々が活躍していますが1つに結集して “地元の力で創り上げるオペラの上演”はありませんでした。その理由の 1 つに資金面が挙げられます。オペラは総勢 170 名が携わる総合芸術。費用が嵩みます。1回の公演で満席(1500 席)でも約 240 万円の赤字となる事業です。ただ、取り組んでみないと進まないと考え、過去の高崎芸術劇場大劇場でのオペラ動員数よりその需要があると踏み、上演に踏み切りました。
●活動:高崎芸術劇場大劇場にて地産地消オペラ「椿姫」の上演
群馬県にゆかりのあるメンバーにて構成されたオペラ「椿姫」を上演致します。プロによる生演奏、プロオペラ歌手による歌唱など、本物の舞台を作ることにこだわって活動しています。この活動が若い世代へ繋がり、“群馬県にて最良の環境で芸術を披露する場がある”という子供達への夢・芸術文化の長期的な発展にも繋がるものと考えております。
●対象:出演者約 170~190 名 観客数:約 1500 名
●回数:年1回 【地産地消オペラ「椿姫」上演】
●合唱練習回数:約 25 回 ・対象人数:オペラ歌手 10 名、合唱 60 名
・内容:イタリア語の発音の仕方、発声練習、音取り、各パート練習、演技指導
●リハーサル:約 3 回
・対象人数:オペラ歌手 10 名、合唱 60 名、ダンサー10 名、プロオーケストラ 40 名、アマチュア楽団 50 名
・内容:オペラの通し稽古、舞台上の場所確認、音量のバランスチェック等